ぶっ飛ぶ円盤
是くの如く我聴けり
ENTRY NAVI
- Home
- クラシック
『白鳥の湖』 チャイコフスキー
 「 俺の『白鳥の湖』では勝てない!」
「 俺の『白鳥の湖』では勝てない!」 ドリーブの 『シルヴィア』 を聴いて、チャイコフスキーが
そう言ったとか、言わなかったとか。
たしかに 『シルヴィア』 には、洗練された美しさがある。
それに比べて 『白鳥の湖』 はイモ臭い。
けれども、それがチャイコフスキー最大の魅力なのだ。
『白鳥の湖』 はスウィートポテトなのである。
オシャレではないけれど、つい手が伸びてしまう。
「音楽が大好きだ!」 という、チャイコフスキー情念が、
ダイレクトに伝わってくる心地よさ があるのだ。
第1幕 第2番 「ワルツ」
チャイコフスキーは、交響曲に [掟やぶりのワルツ挿入] をしてしまうほどの
ワルツバカ、もとい 隠れワルツ王 である。
ワルツといえば優雅なイメージだが、
この曲は、ドラムやシンバルが騒々しく鳴り響く。
しかし、それがために いっそうメロディの美しさが際立つのである。
第2幕 第13番e 「オデットと王子のパ・ダクシオン」
甘美の極み。
美しいハープの音色で始まり、まとわりつく水飴のようなヴァイオリンの旋律。
管楽器が鳴り始めると、旋律は高原のミントのように爽やかに響くが、
やがてまた濃厚な甘さが、憂いとともに襲ってくる。
ベタな展開ではあるが、だからこそ、切なくなること確実。
第3幕 第20番 「チャルダッシュ」
スロウで重たい空気の中で不穏な美しさを放つメロディ。
と突然、音楽は 強く激しく速く なる。(無論、美メロは健在)
この、緩急の落差にやられる。
第4幕 第20番『情景」、第21番「終幕」
魔法によってオディールを花嫁に選んでしまったジークフリートは、
オデットに許しを請う。
そこへ現れた 悪魔ロットバルト。
ジークフリートは怒りに燃えてロットバルトを討ち破るが、
白鳥達の呪いは解けない。
ならば せめて天国で結ばれようと、ジークフリートとオデットは湖に身を投げる。
このラストは 何度聴いても、泣ける。


オデット オディール
『白鳥の湖』 を聴くようになったのは、
小学生の頃、『ドカベン』で、殿馬が、
「秘打 白鳥の湖」などとやっていた頃である。

「そういえば母がレコードを持っていたな」
ふと思い出して かけてみて、はまってしまった。
以来、高校生の頃まで、毎日のように聴いても、飽きることがなかった。
PR
『くるみ割り人形』 チャイコフスキー
クラシックのCDは、同じ曲でも 指揮者、演奏者、録音時期
によって、たくさんのヴァリエーションがある。
“名盤” といわれるものでも、必ず自分が気に入るとはかぎらないので、
結局どれを選べばいいのか、わからない。
もっとも、最初に目にするものを親だと思うヒナのように、
最初に聴いたヴァージョンが、その曲の よしあし の基準になってしまうことも多い。
私が最初に 『くるみ割り人形』 を聴いたのは レコードの時代で、
父が持っていた ソニー・ファミリークラブ クラシック名曲集か何かの中の1枚だったと思う。
CDの時代になって、自分でも 『くるみ割り人形』 を買ったのだが、
どうしても気に入らない。
「金平糖の踊り」 のチェレスタが、何か違うのである。
さらに もう1枚買ったが、これも気にいらない。
「同じ曲なら、どれもたいして違うまい」 と思ったワタクシが馬鹿だった。
“運命の1枚” には、偶然に めぐりあった。
中古CDのワゴンの中に、それは あった。
あまり期待しないで購入し、聴いてみると …
「こ、これだぁ~」
心を掻き乱す、チェレスタの妖しい響き。
『くるみ割り人形』 の“トワイライト・ゾーン”。
このCDの 「金平糖の踊り」 は、今も 聴くたびに ゾクッ とする。



クリスマスプレゼント 人形と鼠の戦い 金平糖の踊り
まぁ、実家のレコードの指揮者・楽団・録音年などを調べ、
「このヴァージョン、CDで出てますか」 と、お店に訊いて、
取り寄せてもらえばよかったのだろうが …
若い頃は、そんなことも思いつかなかったんだなぁ。
チャイコフスキー

によって、たくさんのヴァリエーションがある。
“名盤” といわれるものでも、必ず自分が気に入るとはかぎらないので、
結局どれを選べばいいのか、わからない。
もっとも、最初に目にするものを親だと思うヒナのように、
最初に聴いたヴァージョンが、その曲の よしあし の基準になってしまうことも多い。
私が最初に 『くるみ割り人形』 を聴いたのは レコードの時代で、
父が持っていた ソニー・ファミリークラブ クラシック名曲集か何かの中の1枚だったと思う。
CDの時代になって、自分でも 『くるみ割り人形』 を買ったのだが、
どうしても気に入らない。
「金平糖の踊り」 のチェレスタが、何か違うのである。
さらに もう1枚買ったが、これも気にいらない。
「同じ曲なら、どれもたいして違うまい」 と思ったワタクシが馬鹿だった。
“運命の1枚” には、偶然に めぐりあった。
中古CDのワゴンの中に、それは あった。
あまり期待しないで購入し、聴いてみると …
「こ、これだぁ~」
心を掻き乱す、チェレスタの妖しい響き。
『くるみ割り人形』 の“トワイライト・ゾーン”。
このCDの 「金平糖の踊り」 は、今も 聴くたびに ゾクッ とする。



クリスマスプレゼント 人形と鼠の戦い 金平糖の踊り
まぁ、実家のレコードの指揮者・楽団・録音年などを調べ、
「このヴァージョン、CDで出てますか」 と、お店に訊いて、
取り寄せてもらえばよかったのだろうが …
若い頃は、そんなことも思いつかなかったんだなぁ。
チャイコフスキー


『ヴァイオリン協奏曲』-第1楽章- メンデルスゾーン
メンデルスゾーンの音楽を聴くと、
そのフェリックスという名前に ふさわしく、
幸福な気分になる、といわれる。
 (日本名なら さしずめ、「幸児」 だろうか)
(日本名なら さしずめ、「幸児」 だろうか) 
「陰鬱さに欠ける」 などと評されることもあるが、たしかに、
(ベートーベンのように)眉間に縦皺を寄せたメンデルスゾーンなど想像できない。
だが、陰が足りないからといって、
締まりのない のっぺりとした音楽か というと、決して そうではない。
徹底的に(何しろ裕福だから …) 先人の音楽を研究し、
古典のエキスを自家薬籠中のものとしたうえで、
そこに自らの“夢と詩情の世界”を組み込んでいる。
メンデルスゾーンを聴けば、
井戸田潤でなくとも、思わず あのセリフを叫ぶに違いない。
美しいメロディを聴きたければ、迷わずメンデルスゾーンを選ぶべし。
中でも、甘美(藤山ではないほうの)な世界に どっぷりと浸れるのが、
『ヴァイオリン協奏曲』ホ短調 作品64 第1楽章 である。
多くのヴァイオリニストが その名人芸を録音しているが、
私の お気に入り は、
オイストラフが コンドラシン指揮のソビエト国立交響楽団をバックに
弾いている ヴァージョンである。(VICC-2017)


ヴァイオリンの音色が、とにかく美しい。
かなり濃厚で、灰汁の強い演奏(及び録音)だが、
これがクセになる。これでないと落ち着かない。
唯一の問題は、
あまりに甘美すぎて、ヘヴィーローテーションで聴き過ぎると
胸焼けしそうになることである。
そんな時は、諏訪内晶子のヴァージョン(UCCD-50004)
を聴く。

こちらは、カッチリと仕上げてある。
メンデルスゾーン=甘ったる過ぎる というイメージを覆すべく、
ムードに流されないように感情を律して、
メロディの美しさが前にでるように心掛けている。
砂糖不使用、蜂蜜と果実の天然甘味で作りました、というような
真摯な演奏だ。
そのフェリックスという名前に ふさわしく、
幸福な気分になる、といわれる。
 (日本名なら さしずめ、「幸児」 だろうか)
(日本名なら さしずめ、「幸児」 だろうか) 
「陰鬱さに欠ける」 などと評されることもあるが、たしかに、
(ベートーベンのように)眉間に縦皺を寄せたメンデルスゾーンなど想像できない。
だが、陰が足りないからといって、
締まりのない のっぺりとした音楽か というと、決して そうではない。
徹底的に(何しろ裕福だから …) 先人の音楽を研究し、
古典のエキスを自家薬籠中のものとしたうえで、
そこに自らの“夢と詩情の世界”を組み込んでいる。
メンデルスゾーンを聴けば、
井戸田潤でなくとも、思わず あのセリフを叫ぶに違いない。
美しいメロディを聴きたければ、迷わずメンデルスゾーンを選ぶべし。
中でも、甘美(藤山ではないほうの)な世界に どっぷりと浸れるのが、
『ヴァイオリン協奏曲』ホ短調 作品64 第1楽章 である。
多くのヴァイオリニストが その名人芸を録音しているが、
私の お気に入り は、
オイストラフが コンドラシン指揮のソビエト国立交響楽団をバックに
弾いている ヴァージョンである。(VICC-2017)


ヴァイオリンの音色が、とにかく美しい。
かなり濃厚で、灰汁の強い演奏(及び録音)だが、
これがクセになる。これでないと落ち着かない。
唯一の問題は、
あまりに甘美すぎて、ヘヴィーローテーションで聴き過ぎると
胸焼けしそうになることである。
そんな時は、諏訪内晶子のヴァージョン(UCCD-50004)
を聴く。

こちらは、カッチリと仕上げてある。
メンデルスゾーン=甘ったる過ぎる というイメージを覆すべく、
ムードに流されないように感情を律して、
メロディの美しさが前にでるように心掛けている。
砂糖不使用、蜂蜜と果実の天然甘味で作りました、というような
真摯な演奏だ。
交響曲第3番ハ短調 作品78 第2楽章 第1部 サン=サーンス
交響曲第3番、交響詩『死の舞踏』、組曲『動物の謝肉祭』 が 1枚で聴けるお得盤。
円盤(レコード・CD)の場合、カップリングも意外に大事だ。
お気に入り 1つ目は、
『交響曲第3番』 第2楽章 第1部。
この曲は、まさに サン=サーンスの魅力 を凝縮している。
ベートーヴェンのように重厚で、
それでいて モーツァルトのように軽妙でもあり、
メンデルスゾ-ンのように美しく、
リストのように技巧的、
と、言えば褒めすぎか。
つまりは、クラシックの “おいしさ” を、存分に味わうことができる。
そこには、先人の技法を徹底的に分析し、綿密に再構築する、
ある種の名人芸が感じられる。
では、そういった先達の様式をくっつければ この曲になるのか というと、
もちろん、そうではない。
再構築した上で、予定調和を少し崩してみせる。
崩しても全体が乱れないのは、
コロコロと転がるピアノがアクセントとして効いているからである。
正直に言えば、あまりに良く出来過ぎていて、ややイヤミな感じも。
前後の楽章のバランスがあるとはいえ、
もう少しだけ暴走して欲しかった。
さて、つぎにプッシュするのは、『動物の謝肉祭』 から「水族館」。
そもそも『動物の謝肉祭』は、パーティーの余興用に作曲されたもので、ユーモラスな曲が多い。
だが、その中で、異様な妖しさを放っているのが、「水族館」 である。
弦楽器は、救急車のサイレンのように音を上下させ、不吉な予感を誘う。
そして、小刻みに ふるえる ようなピアノが、不安を撒き散らす。
水族館で感じる “異世界に迷い込んだような錯覚” が、
音の錬金術師 サン=サーンス によって、見事に表現されている。
ちなみに、
この曲で、♪キラリラリラリン♪ と神秘的な響きを聴かせているのは、
アルモニカ という楽器だそうである。
交響曲第4番 ニ短調 作品120 シューマン
たぶん これは、“対立” を表現しているのだろう。
シューマンの交響曲第4番 第3楽章は、
そう思って聴くと、しっくりくる。
大きくいって2つのムードが、交互に繰り返されるのだが、
その2つの間に、“断絶” を感じるのである。
勇壮で緊迫感のあるメロディに聴き入っていると、
突然、おだやかで やさしいメロディに変わるのだ。
そこには、まるで 接続詞を省略した文章を読むような 違和感 がある。
あるいは、速球のあとにスローカーブがくるような 肩すかし感 とでもいおうか。
慣れるまでは、聴いていて いまひとつ スッキリしなかった。
正直に言えば、最初に聴いた時は、
「おい、なんだよ、せっかく盛り上がっていたところなのに …」
と、ちょっとイラッとした。
“対比”が表現される時の よくあるパターンでは、
「今から変わりますよ、ハイ、変わりましたよ」
というような“つなぎ”が入る。
そうすれば、“流れ”が壊れにくいからだろう。
ところが、この曲では、
不親切というか、聴く者を試しているというか、
「わからなければ、わからなくてもいい」
とでも言うように、流れがブツリと寸断される。
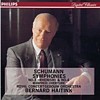 今回 聴いているのは、このCD。 PHCP-10555
今回 聴いているのは、このCD。 PHCP-10555
それでも、また聴きたくなるのが、この曲の魅力。
すると不思議なもので、何回か聴くうちに、解釈が好意的になってくる。
「スムーズさを多少犠牲にしても伝えたかった、文学的な裏メッセージがあったのではないか?」
「なにしろ周さん、ロマンティストだからねぇ」
「ここは、これでいいんだよ」
「シューマンは、こうでなくっちゃ」
「よくやった秀人」
というふうに。
なんだか、思うツボに まんまと ひっかかった気もするが、
聴くたびに評価が変わっていくのもまた、音楽を聴く楽しみの1つだったりするので …
シューマンの交響曲第4番 第3楽章は、
そう思って聴くと、しっくりくる。
大きくいって2つのムードが、交互に繰り返されるのだが、
その2つの間に、“断絶” を感じるのである。
勇壮で緊迫感のあるメロディに聴き入っていると、
突然、おだやかで やさしいメロディに変わるのだ。
そこには、まるで 接続詞を省略した文章を読むような 違和感 がある。
あるいは、速球のあとにスローカーブがくるような 肩すかし感 とでもいおうか。
慣れるまでは、聴いていて いまひとつ スッキリしなかった。
正直に言えば、最初に聴いた時は、
「おい、なんだよ、せっかく盛り上がっていたところなのに …」
と、ちょっとイラッとした。
“対比”が表現される時の よくあるパターンでは、
「今から変わりますよ、ハイ、変わりましたよ」
というような“つなぎ”が入る。
そうすれば、“流れ”が壊れにくいからだろう。
ところが、この曲では、
不親切というか、聴く者を試しているというか、
「わからなければ、わからなくてもいい」
とでも言うように、流れがブツリと寸断される。
それでも、また聴きたくなるのが、この曲の魅力。
すると不思議なもので、何回か聴くうちに、解釈が好意的になってくる。
「スムーズさを多少犠牲にしても伝えたかった、文学的な裏メッセージがあったのではないか?」
「なにしろ周さん、ロマンティストだからねぇ」
「ここは、これでいいんだよ」
「シューマンは、こうでなくっちゃ」
「よくやった秀人」
というふうに。
なんだか、思うツボに まんまと ひっかかった気もするが、
聴くたびに評価が変わっていくのもまた、音楽を聴く楽しみの1つだったりするので …
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(02/06)
(01/09)
(09/05)
(08/20)
(07/15)
(06/07)
(06/06)
(05/02)
(05/01)
(05/01)
(04/10)
(04/09)
(04/08)
(04/07)
(04/06)
(04/05)
(04/04)
(03/31)
(03/31)
最新TB
プロフィール
HN:
Richard Towerchild
性別:
男性
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(03/31)
(03/31)
(04/04)
(04/05)
(04/06)
(04/07)
(04/08)
(04/09)
(04/10)
(05/01)
(05/01)
(05/02)
(06/06)
(06/07)
(07/15)
(08/20)
(09/05)
(01/09)
(02/06)
