ぶっ飛ぶ円盤
是くの如く我聴けり
ENTRY NAVI
- [PR] ()
- 交響曲第3番ハ短調 作品78 第2楽章 第1部 サン=サーンス (クラシック)
- 交響曲第4番 ニ短調 作品120 シューマン (クラシック)
- セレナード第13番ト長調「アイネ クライネ ナハトムジーク」 モーツァルト (クラシック)
- 『ハンガリー狂詩曲』管弦楽版 リスト, ドップラー (クラシック)
- 『PERFECT STRANGERS』 DEEP PURPLE (ハード・ロック )
交響曲第3番ハ短調 作品78 第2楽章 第1部 サン=サーンス
交響曲第3番、交響詩『死の舞踏』、組曲『動物の謝肉祭』 が 1枚で聴けるお得盤。
円盤(レコード・CD)の場合、カップリングも意外に大事だ。
お気に入り 1つ目は、
『交響曲第3番』 第2楽章 第1部。
この曲は、まさに サン=サーンスの魅力 を凝縮している。
ベートーヴェンのように重厚で、
それでいて モーツァルトのように軽妙でもあり、
メンデルスゾ-ンのように美しく、
リストのように技巧的、
と、言えば褒めすぎか。
つまりは、クラシックの “おいしさ” を、存分に味わうことができる。
そこには、先人の技法を徹底的に分析し、綿密に再構築する、
ある種の名人芸が感じられる。
では、そういった先達の様式をくっつければ この曲になるのか というと、
もちろん、そうではない。
再構築した上で、予定調和を少し崩してみせる。
崩しても全体が乱れないのは、
コロコロと転がるピアノがアクセントとして効いているからである。
正直に言えば、あまりに良く出来過ぎていて、ややイヤミな感じも。
前後の楽章のバランスがあるとはいえ、
もう少しだけ暴走して欲しかった。
さて、つぎにプッシュするのは、『動物の謝肉祭』 から「水族館」。
そもそも『動物の謝肉祭』は、パーティーの余興用に作曲されたもので、ユーモラスな曲が多い。
だが、その中で、異様な妖しさを放っているのが、「水族館」 である。
弦楽器は、救急車のサイレンのように音を上下させ、不吉な予感を誘う。
そして、小刻みに ふるえる ようなピアノが、不安を撒き散らす。
水族館で感じる “異世界に迷い込んだような錯覚” が、
音の錬金術師 サン=サーンス によって、見事に表現されている。
ちなみに、
この曲で、♪キラリラリラリン♪ と神秘的な響きを聴かせているのは、
アルモニカ という楽器だそうである。
PR
交響曲第4番 ニ短調 作品120 シューマン
たぶん これは、“対立” を表現しているのだろう。
シューマンの交響曲第4番 第3楽章は、
そう思って聴くと、しっくりくる。
大きくいって2つのムードが、交互に繰り返されるのだが、
その2つの間に、“断絶” を感じるのである。
勇壮で緊迫感のあるメロディに聴き入っていると、
突然、おだやかで やさしいメロディに変わるのだ。
そこには、まるで 接続詞を省略した文章を読むような 違和感 がある。
あるいは、速球のあとにスローカーブがくるような 肩すかし感 とでもいおうか。
慣れるまでは、聴いていて いまひとつ スッキリしなかった。
正直に言えば、最初に聴いた時は、
「おい、なんだよ、せっかく盛り上がっていたところなのに …」
と、ちょっとイラッとした。
“対比”が表現される時の よくあるパターンでは、
「今から変わりますよ、ハイ、変わりましたよ」
というような“つなぎ”が入る。
そうすれば、“流れ”が壊れにくいからだろう。
ところが、この曲では、
不親切というか、聴く者を試しているというか、
「わからなければ、わからなくてもいい」
とでも言うように、流れがブツリと寸断される。
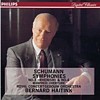 今回 聴いているのは、このCD。 PHCP-10555
今回 聴いているのは、このCD。 PHCP-10555
それでも、また聴きたくなるのが、この曲の魅力。
すると不思議なもので、何回か聴くうちに、解釈が好意的になってくる。
「スムーズさを多少犠牲にしても伝えたかった、文学的な裏メッセージがあったのではないか?」
「なにしろ周さん、ロマンティストだからねぇ」
「ここは、これでいいんだよ」
「シューマンは、こうでなくっちゃ」
「よくやった秀人」
というふうに。
なんだか、思うツボに まんまと ひっかかった気もするが、
聴くたびに評価が変わっていくのもまた、音楽を聴く楽しみの1つだったりするので …
シューマンの交響曲第4番 第3楽章は、
そう思って聴くと、しっくりくる。
大きくいって2つのムードが、交互に繰り返されるのだが、
その2つの間に、“断絶” を感じるのである。
勇壮で緊迫感のあるメロディに聴き入っていると、
突然、おだやかで やさしいメロディに変わるのだ。
そこには、まるで 接続詞を省略した文章を読むような 違和感 がある。
あるいは、速球のあとにスローカーブがくるような 肩すかし感 とでもいおうか。
慣れるまでは、聴いていて いまひとつ スッキリしなかった。
正直に言えば、最初に聴いた時は、
「おい、なんだよ、せっかく盛り上がっていたところなのに …」
と、ちょっとイラッとした。
“対比”が表現される時の よくあるパターンでは、
「今から変わりますよ、ハイ、変わりましたよ」
というような“つなぎ”が入る。
そうすれば、“流れ”が壊れにくいからだろう。
ところが、この曲では、
不親切というか、聴く者を試しているというか、
「わからなければ、わからなくてもいい」
とでも言うように、流れがブツリと寸断される。
それでも、また聴きたくなるのが、この曲の魅力。
すると不思議なもので、何回か聴くうちに、解釈が好意的になってくる。
「スムーズさを多少犠牲にしても伝えたかった、文学的な裏メッセージがあったのではないか?」
「なにしろ周さん、ロマンティストだからねぇ」
「ここは、これでいいんだよ」
「シューマンは、こうでなくっちゃ」
「よくやった秀人」
というふうに。
なんだか、思うツボに まんまと ひっかかった気もするが、
聴くたびに評価が変わっていくのもまた、音楽を聴く楽しみの1つだったりするので …
セレナード第13番ト長調「アイネ クライネ ナハトムジーク」 モーツァルト
モーツァルトといえば、この作品!
いくらポピュラーだからといって、E.K.N などと略さないように。
Eine Kleine Nachtmusik という響きが また何とも雅やかなのだから。
この作品は、徹底的な娯楽音楽であると同時に、一分の隙もない完璧な芸術でもある。
そこが、すばらしい。
第1楽章
我々の世代なら、ヴィックス・ドロップのCM、♪ばーか、ばーか、エヘン虫~♪、
ヤングの諸君には、♪おーふろー で バスロマン~♪、
で おなじみ。
ウィットに富んだ会話を聞いているような、
華やかで 軽やかな メロディが耳に残る。
第2楽章
優雅で おだやかな 旋律。
気だるいような、暖かいような気分に身をゆだねていると、
にわかに動きがある。少し緊張するが、
すぐにまた、ゆったりとしたムードに戻り、ほっ と しながら 終る。
第3楽章
宮殿の広間で奏でられているような音楽。
短いが、軽い高揚感がある。
第4楽章
ウキウキと跳ねるような躍動感。
何だか せかせかと あわただしい。
そして、やったぜ、という感じ(!?)で大団円。
嗚呼、この作品のような、
優しくて、暖かくて、愉快な
人物になりたい。


いくらポピュラーだからといって、E.K.N などと略さないように。
Eine Kleine Nachtmusik という響きが また何とも雅やかなのだから。
この作品は、徹底的な娯楽音楽であると同時に、一分の隙もない完璧な芸術でもある。
そこが、すばらしい。
第1楽章
我々の世代なら、ヴィックス・ドロップのCM、♪ばーか、ばーか、エヘン虫~♪、
ヤングの諸君には、♪おーふろー で バスロマン~♪、
で おなじみ。
ウィットに富んだ会話を聞いているような、
華やかで 軽やかな メロディが耳に残る。
第2楽章
優雅で おだやかな 旋律。
気だるいような、暖かいような気分に身をゆだねていると、
にわかに動きがある。少し緊張するが、
すぐにまた、ゆったりとしたムードに戻り、ほっ と しながら 終る。
第3楽章
宮殿の広間で奏でられているような音楽。
短いが、軽い高揚感がある。
第4楽章
ウキウキと跳ねるような躍動感。
何だか せかせかと あわただしい。
そして、やったぜ、という感じ(!?)で大団円。
嗚呼、この作品のような、
優しくて、暖かくて、愉快な
人物になりたい。
『ハンガリー狂詩曲』管弦楽版 リスト, ドップラー
異国情緒と同時に、親しみやすさを感じる、そんな作品。
作者は、この人、
 … ではなくて … こちら
… ではなくて … こちら 
フランツ・リスト。
ピアノ独奏用の作品集の中から、6曲を選んで 管弦楽用にアレンジ。
その際に協力したのが、フランツ・ドップラー。

 ピ~ポ~ ピーポー PEOPLE~
ピ~ポ~ ピーポー PEOPLE~
ドップラー効果で有名な、クリスチャン・ドップラーとは、もちろん別人。
管弦楽版には、数種類のヴァージョンがあるらしいのだが、
今回聴くのは、これ。
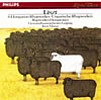 クルト・マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1984年録音
クルト・マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1984年録音
第1番
原曲14番
第2番
原曲2番。
♪パパーン♪ となると、「ああ 、またか、もう聴き飽きたヨ」と言いたくなるくらい有名。
でも急速部になると … 何度聴いても、やっぱり気分が高揚してしまう。
まぁ、一種の“刷り込み”である。
この後半部のメロディは、ネッケの「クシコスポスト」にも使われ、
「クシコスポスト」は運動会のBGMとして流れているから。
この旋律を聴くと、条件反応としてノルアドレナリンが出てしまうのである。
第3番
原曲6番
第4番
原曲12番。
どうも この4番と、次の5番は、ピアノ版のほうが、スッキリとしていて聴きやすい印象。
管弦楽版は、多彩な変化というか、こまごま し過ぎているというか。
超絶技巧愛好家のリスト先生が、
「あの技法も使いたい、この効果も まだ使ってない」
「せっかく6曲あるのだから、ちがった味付けのアレンジをしたい」
などと張り切ったのではないか、と想像すると楽しい。
第5番
原曲5番
第6番
原曲9番。
出だしの部分を聴いていると、「埴生の宿」(ホーム スウィート ホーム)のメロディを連想した。
♪お正月には凧揚げて~♪(「お正月」)
からの
♪と~し の は~じめ~の♪(「一月一日」)
への連続技


作者は、この人、
フランツ・リスト。
ピアノ独奏用の作品集の中から、6曲を選んで 管弦楽用にアレンジ。
その際に協力したのが、フランツ・ドップラー。
ドップラー効果で有名な、クリスチャン・ドップラーとは、もちろん別人。
管弦楽版には、数種類のヴァージョンがあるらしいのだが、
今回聴くのは、これ。
第1番
原曲14番
第2番
原曲2番。
♪パパーン♪ となると、「ああ 、またか、もう聴き飽きたヨ」と言いたくなるくらい有名。
でも急速部になると … 何度聴いても、やっぱり気分が高揚してしまう。
まぁ、一種の“刷り込み”である。
この後半部のメロディは、ネッケの「クシコスポスト」にも使われ、
「クシコスポスト」は運動会のBGMとして流れているから。
この旋律を聴くと、条件反応としてノルアドレナリンが出てしまうのである。
第3番
原曲6番
第4番
原曲12番。
どうも この4番と、次の5番は、ピアノ版のほうが、スッキリとしていて聴きやすい印象。
管弦楽版は、多彩な変化というか、こまごま し過ぎているというか。
超絶技巧愛好家のリスト先生が、
「あの技法も使いたい、この効果も まだ使ってない」
「せっかく6曲あるのだから、ちがった味付けのアレンジをしたい」
などと張り切ったのではないか、と想像すると楽しい。
第5番
原曲5番
第6番
原曲9番。
出だしの部分を聴いていると、「埴生の宿」(ホーム スウィート ホーム)のメロディを連想した。
♪お正月には凧揚げて~♪(「お正月」)
からの
♪と~し の は~じめ~の♪(「一月一日」)
への連続技
『PERFECT STRANGERS』 DEEP PURPLE
当時は、早い人だと小学校高学年頃から聴き始めたそうだが、
ワタクシが “ロック” に目覚めたのは、高校生の時だった。
ある日、ラジオから
「PERFECT STRANGERS」 という曲が流れてきた。
なんでも、伝説のロックバンド ディープ・パープル が“復活”した という。
うわ、この曲カッコイイ、と曲の途中から慌ててカセットテープ(古い!)に録音した。
3曲続けてということだったので、
「KNOCKING AT YOUR BACK DOOR」 と 「A GYPSY'S KISS」 は、丸々 録音できた。
それまでにも、ビートルズだとか、ストーンズだとか、
いわゆる“ロック”系の曲は耳にしたことがあったはずだが、
ふ~ん そんな曲があるのか、という程度で、特にカッコイイとは思わなかった。
ディープ・パープルを カッコイイ と思ったのは、
(今 思えば)ロックのビートに
クラシックのように美しく、歌謡曲のようにポップな メロディが ミックスされていたからだろう。
それでも、この時に聴いていなければ、
好きになることはなかったかもしれないが。
思い出話は これくらいにして …

ディープ・パープルの復活アルバム 『PERFECT STRANGERS』 は、
1984年に発売された。
全盛期をリアルタイムで経験されている方は まだ物足りない という。
しかし、ワタクシ達のような後追い組には、
十二分過ぎるほどに魅力的なアルバムである。

リッチー・ブラックモアは、極上のフレーズを 流れるように 紡ぎ出していく。
少し前まで RAINBOWで 「FIRE DANCE」 や 「MAKE YOUR MOVE」を弾いていたのだから、
まだまだ派手なプレイも出来たはずだが、
ここでは ギターを歌わせる ことを より心掛けているようである。

イアン・ギランの声は、年を重ねて魅力が増した。
若い頃のようなモンスター・シャウトは使えなくても、
全身全霊を込めた、豊かな歌心に魂が震えた。
(その後、また酒に溺れてしまうのだが … )
この歌を「下手だ」という人がいるのが信じられない。

本人は もう少し実験的なプレイも演りたかったかもしれないが、
ジョン・ロードほど、ツボを抑えた演奏が出来る人はいない。
痒いところに手が届く というか、
そう そこ そこ う~ん いいトコ突いてくるな~ という感じ。
彼のキーボードのおかげで、曲がグッと引き締まる。

RAINBOW時代は リッチーのサポートに徹していた ロジャー・グローヴァーだが、
昔を思い出してか、少し前に出てきている。
『MACHINE HEAD』あたりを 密かに聴き直している姿を想像すると楽しい。
独特のベースラインも健在。

贅沢を言えば、イアン・ペイスのドラムは、ちょっと平板な気がする。
人一倍 “音” に こだわってきた人のはずなのに …
力量を出し切れていない感じ。もったいない。
サポートに徹するにしても、職人芸的カッコよさを発揮できると思うのだが。


ワタクシが “ロック” に目覚めたのは、高校生の時だった。
ある日、ラジオから
「PERFECT STRANGERS」 という曲が流れてきた。
なんでも、伝説のロックバンド ディープ・パープル が“復活”した という。
うわ、この曲カッコイイ、と曲の途中から慌ててカセットテープ(古い!)に録音した。
3曲続けてということだったので、
「KNOCKING AT YOUR BACK DOOR」 と 「A GYPSY'S KISS」 は、丸々 録音できた。
それまでにも、ビートルズだとか、ストーンズだとか、
いわゆる“ロック”系の曲は耳にしたことがあったはずだが、
ふ~ん そんな曲があるのか、という程度で、特にカッコイイとは思わなかった。
ディープ・パープルを カッコイイ と思ったのは、
(今 思えば)ロックのビートに
クラシックのように美しく、歌謡曲のようにポップな メロディが ミックスされていたからだろう。
それでも、この時に聴いていなければ、
好きになることはなかったかもしれないが。
思い出話は これくらいにして …
ディープ・パープルの復活アルバム 『PERFECT STRANGERS』 は、
1984年に発売された。
全盛期をリアルタイムで経験されている方は まだ物足りない という。
しかし、ワタクシ達のような後追い組には、
十二分過ぎるほどに魅力的なアルバムである。

リッチー・ブラックモアは、極上のフレーズを 流れるように 紡ぎ出していく。
少し前まで RAINBOWで 「FIRE DANCE」 や 「MAKE YOUR MOVE」を弾いていたのだから、
まだまだ派手なプレイも出来たはずだが、
ここでは ギターを歌わせる ことを より心掛けているようである。

イアン・ギランの声は、年を重ねて魅力が増した。
若い頃のようなモンスター・シャウトは使えなくても、
全身全霊を込めた、豊かな歌心に魂が震えた。
(その後、また酒に溺れてしまうのだが … )
この歌を「下手だ」という人がいるのが信じられない。

本人は もう少し実験的なプレイも演りたかったかもしれないが、
ジョン・ロードほど、ツボを抑えた演奏が出来る人はいない。
痒いところに手が届く というか、
そう そこ そこ う~ん いいトコ突いてくるな~ という感じ。
彼のキーボードのおかげで、曲がグッと引き締まる。
RAINBOW時代は リッチーのサポートに徹していた ロジャー・グローヴァーだが、
昔を思い出してか、少し前に出てきている。
『MACHINE HEAD』あたりを 密かに聴き直している姿を想像すると楽しい。
独特のベースラインも健在。

贅沢を言えば、イアン・ペイスのドラムは、ちょっと平板な気がする。
人一倍 “音” に こだわってきた人のはずなのに …
力量を出し切れていない感じ。もったいない。
サポートに徹するにしても、職人芸的カッコよさを発揮できると思うのだが。


カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(02/06)
(01/09)
(09/05)
(08/20)
(07/15)
(06/07)
(06/06)
(05/02)
(05/01)
(05/01)
(04/10)
(04/09)
(04/08)
(04/07)
(04/06)
(04/05)
(04/04)
(03/31)
(03/31)
最新TB
プロフィール
HN:
Richard Towerchild
性別:
男性
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(03/31)
(03/31)
(04/04)
(04/05)
(04/06)
(04/07)
(04/08)
(04/09)
(04/10)
(05/01)
(05/01)
(05/02)
(06/06)
(06/07)
(07/15)
(08/20)
(09/05)
(01/09)
(02/06)
